MEMBER PAGE
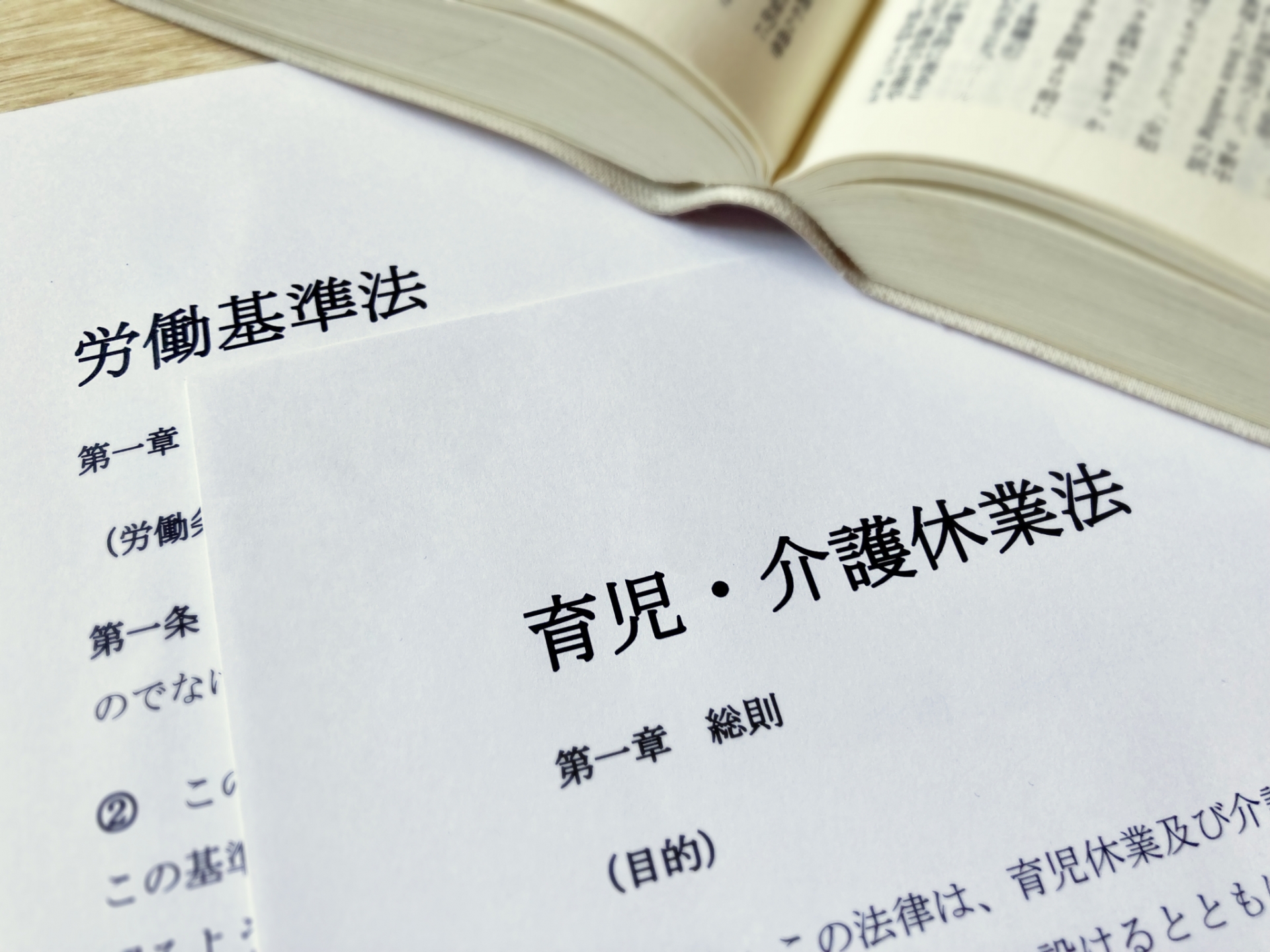
2025年4月に施行される育児・介護休業法の改正では、企業が新たに取り組むべき義務が明確化されています。本改正は、少子高齢化や多様な働き方への対応を目的としており、企業の人事制度や就業規則に直接影響を及ぼします。以下に、改正内容を詳細に解説するとともに、具体的な対応策を提案します。
少子化対策や高齢化社会への対応が急務となる中、政府は働く人々が育児や介護を理由に仕事を諦めることなく、柔軟に働ける環境を整えるための法改正を進めています。今回の改正では以下の3つが特に重要です。
子育て世代が職場に残りながら家庭を支えるための環境整備が求められます。
高齢者介護を理由とする離職を防ぎ、労働力の減少に歯止めをかけるため、企業の取り組みが義務化されます。
テレワークの導入や労働時間の短縮など、働き方改革を支える施策が強化されます。
以下は、2025年4月1日から適用される主な改正内容です。
従来の「半日単位」での取得が中心だった子の看護休暇が、より短い時間単位(1時間単位など)でも取得可能になります。
このことによって、急な体調不良や学校行事への参加がしやすくなります。
・就業規則を改訂し、時間単位での休暇取得を明記する。
・申請手続きの簡略化と、休暇取得を促進する制度の周知。
3歳未満の子を養育する従業員が請求した場合、事業運営に著しい支障がない限り、所定外労働(残業)を命じることができません。この規定により、ワークライフバランスの確保が進むとされています。
・残業の抑制を図るため、タスク管理や人員配置を見直す。
・残業を削減するためのITツールや業務効率化プロジェクトを導入。
育児や介護を理由に柔軟な働き方を求める従業員に対し、テレワークを導入する努力義務が新設されました。これは、短時間勤務制度の代替措置としても活用できます。
・テレワーク制度の導入を検討し、対象業務や対象者の条件を整備する。
・ITインフラの強化や、従業員のテレワーク利用に対するトレーニングを実施。
これまで対象外だった中小企業にも、育児休業取得状況の公表が義務付けられます。具体的には、男女別の取得率を企業ウェブサイトや会社案内などに記載する必要があります。
・育児休業の取得率を把握し、定期的に集計する仕組みを構築。
・公表内容を分かりやすくまとめ、ウェブサイトなどで適切に周知。
介護休暇が取得可能な対象者の範囲が広がり、利用のハードルが低くなります。また、個別の周知や意向確認が義務化され、介護に直面する従業員への支援が強化されます。
・介護休暇に関する相談窓口を設置し、従業員への情報提供を行う。
・管理職に対し、介護に直面した従業員への配慮や対応方法を教育する。
改正法は企業にとって追加の負担をもたらす可能性がありますが、適切に対応することで、以下のような効果が期待されます。
柔軟な制度を導入することで、従業員が安心して働ける環境を提供できます。
育児や介護を理由とする離職を防ぎ、労働力の確保につながります。
法改正への積極的な対応は、採用活動や取引先との関係においてもプラスの影響を与えます。
2025年4月の育児・介護休業法改正は、企業にとって新たな負担を意味する一方で、従業員満足度の向上や離職率の低下といったプラスの側面を持つ重要なチャンスでもあります。長期的な視点で労働環境を整備することで、従業員のエンゲージメントや企業価値の向上を実現していきましょう。
なお、弊社では、この改正に対応するための 「育児・介護休業法対応マニュアル」 を作成し、ご希望の企業様に配布しております。本マニュアルでは、改正内容の詳細な解説や実務で活用できるポイントを網羅しておりますので、ぜひご活用ください。
ご希望の場合は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
どのような疑問ご相談でもお気軽にお問い合わせください。
守秘義務により、外部に秘密がもれることは絶対にありませんのでご安心下さい。