MEMBER PAGE
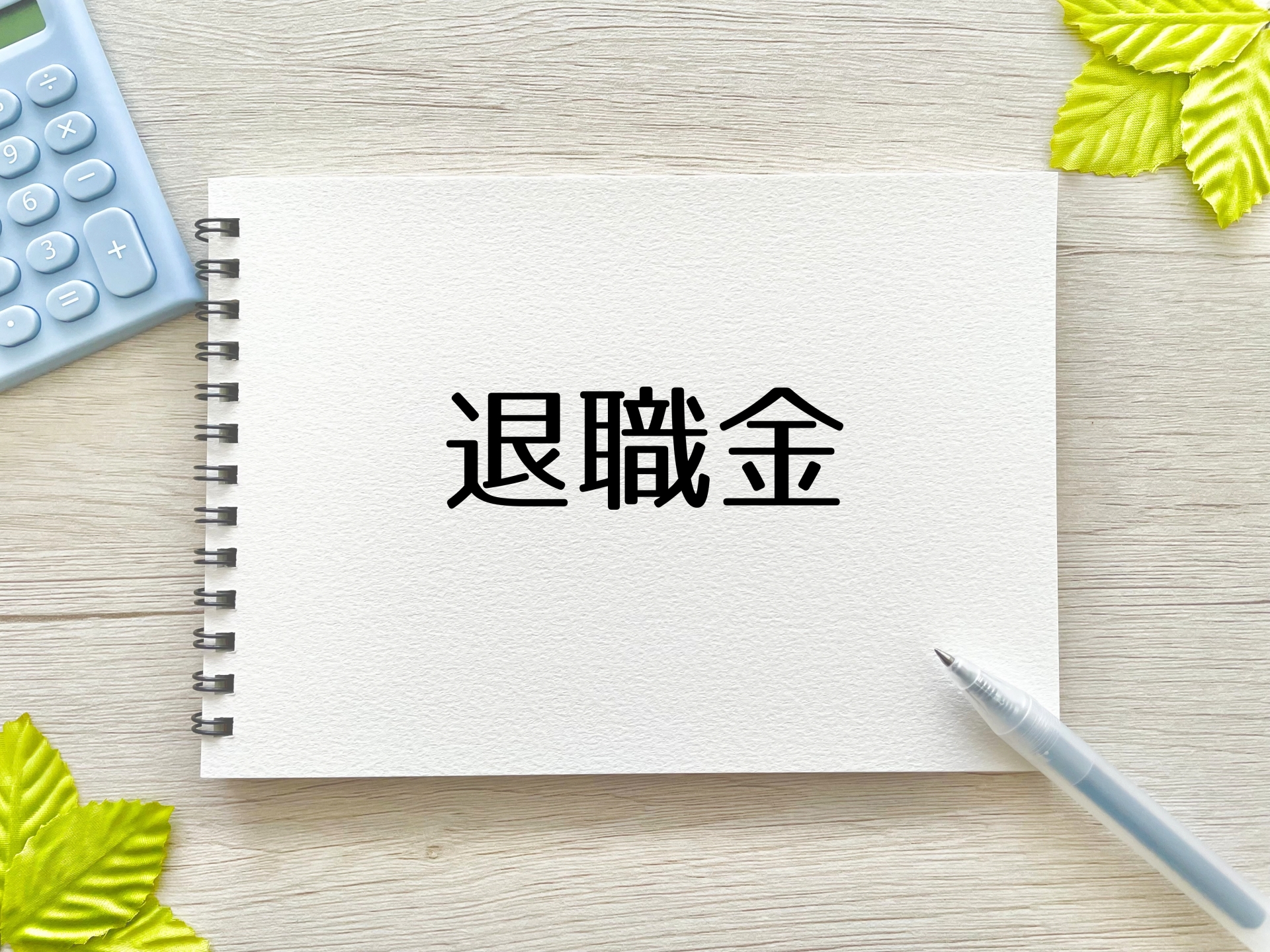
今年もいよいよ終わりが近づいてきました。本稿では、今年最後のテーマとして「退職金制度」について深掘りしたいと思います。
退職金は、従業員が退職時に受け取る金銭的な給付であり、従業員と企業との長期間の関係の中で重要な役割を果たすものです。
しかし、その性質についてはさまざまな説があります。代表的なものを以下に挙げます。
長年勤めあげた従業員の貢献に対する報酬として支給する考え方です。特に勤続年数が重視され、会社への長期的なコミットメントを評価する仕組みです。
在職中の賃金の一部を後払いで支給するという考え方です。この場合、退職金は在職期間中の労働の対価の一部として位置づけられます。
退職後の生活を安定させるための保障として支給されるものです。特に高齢者向けの生活保障としての意味が強調されます。
このほかにも、慣習に基づくものや、労働契約の清算として位置づける考え方などがあります。
退職金をどのように設計し、捉えるかは、企業の人事戦略や経営方針に大きな影響を与えます。それぞれの説について具体的に検討してみましょう。
この説は、勤続年数や終身雇用を重視します。しかし、現代の日本における雇用環境は流動化が進んでおり、終身雇用や年功序列の仕組みは崩れつつあります。
そのため、功労報償説に基づく退職金制度は、中途採用者にとって魅力が乏しく、求人力の向上には繋がりにくいと考えられます。
従業員の生活保障という観点は社会的な意義があるものの、企業側にとっては「コスト負担」という側面が大きくなりがちです。
また、これを退職金の主目的とする場合、在職中のモチベーション向上には直結しない可能性があります。
賃金後払い説では、退職金を賃金の延長と位置づけ、人事評価や給与体系と強く連動させることが可能です。
この仕組みによって、退職金制度が単なる「退職後の給付」ではなく、「在職中の評価」と結びつき、モチベーションを高めるインセンティブとして機能します。
ポイント制退職金制度は、従来の「基本給×係数」に基づく退職金制度とは異なり、以下のような構造を持っています。
勤続年数、役職の在籍期間、人事評価のスコアなどをポイントとして積み上げます。
※計算方法の例
人事評価30点の社員が10年勤務した場合、300ポイントが蓄積されます。
一方、人事評価80点の社員が4年勤務した場合は320ポイントとなり、短期間であっても高評価の社員がより多くの退職金を得られる仕組みです。
このように、ポイント制退職金制度は以下の効果を期待できます。
・中途採用者や高評価の社員にとって魅力的な制度となるため、求人力が向上する。
・退職金を人事評価や成果主義と連動させることで、企業全体のポリシーに統一性が生まれ、従業員のモチベーション向上に寄与する。
退職金制度は、社員の行動管理や懲戒においても重要な役割を果たします。例えば、以下のような規定を退職金規程に盛り込むことが推奨されます。
過去の懲戒処分が退職金額に影響することを明記する。
引継ぎを怠った場合や、会社との合意なく一方的に退職した場合、退職金の減額措置を取る。
これにより、問題行動や懲戒対象となる社員に対して適切な対応が可能となり、企業全体の秩序維持やリスク管理にもつながります。
また、勤続年数の長い社員、役職者などは退職金への影響が大きいことから、さらに強いコントロール下におかれ、強いリスク管理が可能となります。
退職金制度は単なる退職時の金銭給付にとどまらず、人事戦略や経営方針の中核を担う重要な要素です。
特に、賃金後払い説やポイント制退職金制度を採用することで、求人力の強化や従業員のモチベーション向上、組織全体の統制に寄与します。
ただし、退職金制度を変更する際は、従業員に不利益変更と受け取られないよう十分な注意が必要です。
変更の設計や運用においては、専門家のアドバイスを受けることでトラブルを未然に防ぐことができます。
退職金制度の見直しや導入についてご不明な点がありましたら、ぜひ弊社にお問い合わせください。
どのような疑問ご相談でもお気軽にお問い合わせください。
守秘義務により、外部に秘密がもれることは絶対にありませんのでご安心下さい。